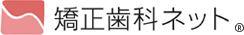顎関節症診療ガイドライン:その理解のために
- 座長 :
- 小林 義典 先生
- 講演者 :
- 杉崎 正志 先生
講演会場は200席ほど座席があり、講演が始まるころにはほぼ満席でした。顎関節症について、症例を踏まえながら講演されました。
概要は、「咀嚼筋に対するスタビライゼーションスプリントは有効か」「開口障害に対する自己開口訓練、咬合調整は有効か」です。
顎関節症の痛みについて
咀嚼筋に対するスタビライゼーションスプリントは有効かについて一般歯科医師向けにまとめられたものによると、咀嚼筋痛を主訴とする顎関節症患者において、適応症、治療、治療目的、治療による害や負担、他の治療の可能性も含めて十分なインフォームド・コンセントを行うことが出来れば上顎型スタビライゼーションスプリントは使用しても良いが、必ずしも使用をすすめているわけではない。咀嚼筋痛に関しては、マッサージで治る場合が多いとのことでした。
開口障害に対する自己開口訓練は、関節円板のことを患者が十分に理解し、保守的に開口訓練を行い、必ずしも鎮痛剤を使用した方が良いというわけではないと述べられていました。
薬剤の使用方法、薬剤の種類について、また、顎関節症の痛みについては、生体の防衛反応であるので、痛みが出た場合は、顎関節症の痛みが出る行動は、控えたいこと。痛み止めで抑えて、負担になる行動をとると、痛み止めが切れたときに、さらに強い痛みになる可能性があります。顎関節症を有する患者様の咬合調整は、できるだけ行わないことを推奨されていました。
顎関節症の診断の注意点
また顎関節症治療を再考する際、除外、鑑別診断をし、顎関節症と診断するということの大切さについて述べられていました。
- 神経欠落症状、安静時痛の有無、外傷の既往、現病歴などを確認しすること。
- TCH(Tooth Contacting Habit : 歯列接触癖)の管理においては、患者様と歯科医師の共同作業で治療すること。
- 歯が触れていることを自覚してもらうことを知ってもらい、その習慣をやめるようにしていくこと。
- 患者様の日常生活において、15分以上同じ姿勢でいる、頬杖をつく、枕、睡眠時の姿勢、パソコンを使う仕事であれば正しい姿勢をとっているか、痛みが起こったときのこと、いつ1番痛いかなどをしっかりと話を聞くこと。
- 思い込みでの診断はしないように気を付ける。
と注意点についても述べられていました。
開口練習に関しては、患者様と治療のゴールを設け機能障害の改善をゴールとすること、終診ではなく自己管理に移行すること…と患者様と一緒に治療していく重要性、顎関節症の原因、診断、診断後の治療法、治療後の管理について講演されました。