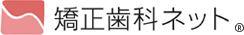目次
親知らずってどうして生えるの?

永久歯は上顎、下顎16本ずつの全部で32本あります(歯そのものが存在しない場合は除きます。)永久歯の中で最後に生えてくる歯を親知らず(または、第3大臼歯や智歯)といい、20歳前後に歯並びの一番奥(第2大臼歯の後ろ)に生えてきます。下記のイラストでは8の第3大臼歯のことを指します。この親知らずは、お口の中でトラブルの原因となることはよく知られていますが、何故そうなってしまうのでしょうか。
食品を加工せずに食べていた大昔と比べ、食生活の変化により、あまり硬いものを噛まなくなったため、顎は退化して小さくなってきました。しかし、歯の大きさや本数にあまり変わりはありません。そのため、永久歯の中で最後に生えてくる親知らずのためのスペースがなく、ほかの歯と同じようにまっすぐ生えることができず、お口の中で悪い影響をもたらすことが増えてきたのです。
親知らずはすべて抜くの?
お口の中できちんと使える場合や、お口にトラブルを引き起こしていない親知らずであれば、抜歯の必要はありません。
【抜歯の必要がない場合の例】
上下の親知らずがしっかりと噛み合い、歯磨きがきちんとできる場合
完全に顎(骨)の中に埋まり、痛みなどの症状が無い場合
親知らずを抜くときはどんな場合?
お口の中でなんらかのトラブルが生じた場合は、抜歯が必要となります。
まっすぐ生えていない場合
生えるスペースが小さく、斜めや横に生えてしまった親知らずは、歯ブラシをきちんとあてることが難しくなります。磨き残しは、虫歯や歯周病の原因となります。そのまま放置しておくと、身身体の抵抗力が落ちたときに突発的に親知らず周辺の歯茎が腫れて痛みを伴い、ときには口を開けることができなくなることがあります。
噛み合う歯が無い場合
まっすぐに生えた親知らずでも、噛み合う歯が無ければ、対する歯茎(上の親知らずなら下の歯茎、下の親知らずなら上の歯茎)にあたるまで伸びてしまい、痛みを引き起こすことがあります。
ほかの歯に悪影響がでる場合
親知らずがまっすぐ生えないために、手前にある第2大臼歯のブラッシングが難しくなり、虫歯や歯周病の可能性が高くなったり、第2大臼歯を押す力が働き、歯並びを悪くするなどの悪影響をもたらすことが考えられます。
治療に悪影響がある場合
矯正治療やインプラント治療を行う際に、親知らずがあることで、歯並びや噛み合わせに悪影響がでることが考えられます。
お口にトラブルが起きる前に抜いた方がいい人は?
親知らずが、お口の中で悪影響をもたらす懸念がある生え方をしている方は、お口のトラブル・症状が出る前に抜いておくことをお勧めいたします。その中でも下記に該当する方は、早めに歯科医院に相談し、検討されてはいかがでしょうか。
受験や仕事で忙しい人?
疲れ・ストレスや、風邪などの身体調不良によって、突発的に炎症が起き、親知らず周辺の歯茎が腫れることがあります。炎症が起きた場合、痛み止めの麻酔が効きづらいため、すぐに抜くことができず、抗生剤を服用し炎症が治まるまで待たなければいけないケースもあります。強く痛みがでると、痛み止めの服用薬が効きづらいこともあります。
結婚を控えている女性
妊娠した場合、炎症を抑える治療や、抜歯をするために薬を使うと胎児に影響が出ることが考えられるため、治療が難しくなります。このように親知らずは、生え方やお口全体の状態によって、「抜く・歯を抜かない」の判断が異なります。ライフスタイルの変化によって、その判断が変わることもあるので、日頃よりかかりつけの歯科医院で定期的な検診を受け、相談しやすい環境をつくっておきましょう。